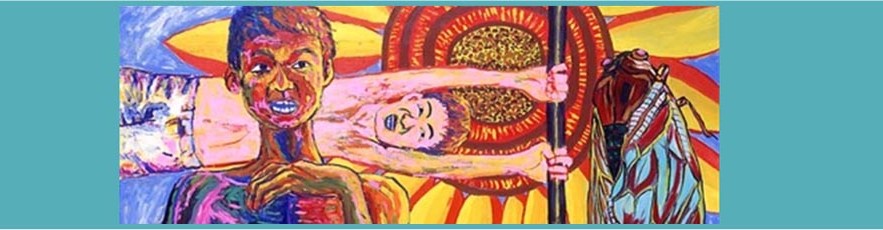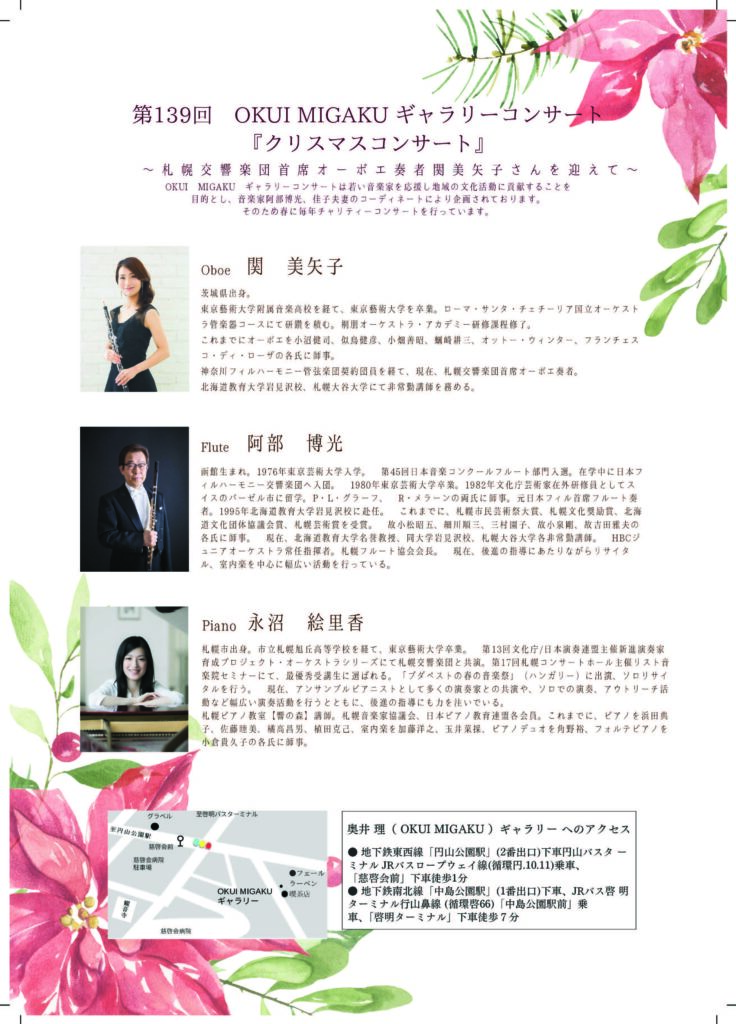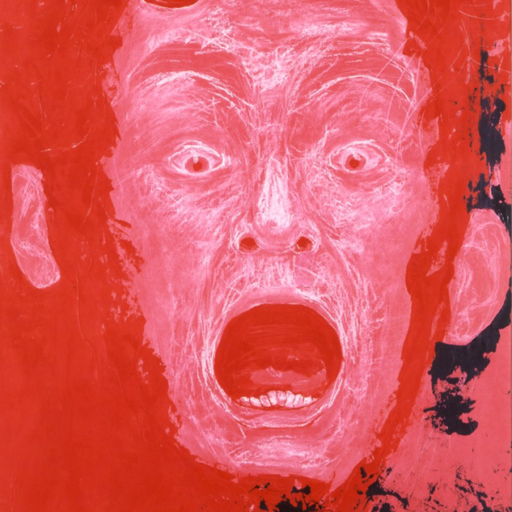第144回OKUI MIGAKUギャラリーコンサート CHRISTMAS CONCERT 札幌交響楽団コンサートマスター会田莉凡さんを迎えて
2025年12月7日(日)16:30開演16:00開場 バイオリン会田莉凡 フルート 阿部博光 ピアノ 阿部佳子
Program~
~J.S.バッハのタベ~
・トリオ・ソナタ ト長調BWV1038
・ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第3番ホ長調 BWV1016
・「音楽の捧げ物」より トリオ・ソナタハ短調BWV1079 ほか
ケット一般4000円 学生3000円 中学生以下2000円